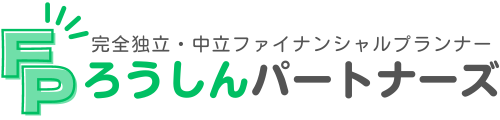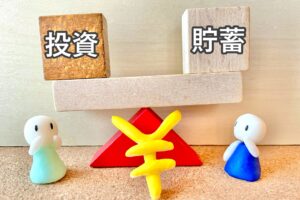2024年1月に新NISAがスタートして2ヶ月が経過しました。
「旧NISA(つみたてNISAや一般NISA)から継続しているけれど、新NISAになって何が変わったのかイマイチわからない」という方も多いと思います。
そこで今回は、新NISA制度についてのよくある誤解を5つ紹介します。
新制度では、旧制度の制限が大きく緩和され、個人の資産形成により有利な制度となっています。
違いをよく理解して、より自分に合った資産運用を続けていくきっかけにしていただければ幸いです。
旧NISAから継続している人だけでなく、これからNISAを始めたいという方にも参考になると思いますので、最後までご覧ください。
誤解①:旧NISAからの移行手続きが必要
旧NISAから新NISAへは、手続きなしで移行できます。
旧NISAの口座(つみたてNISAもしくは一般NISA)を持っていた人は、同じ金融機関で新NISA口座が自動開設されています。
また、旧NISAの積立設定は、そのまま新NISAに引き継ぎされています。
旧つみたてNISAは新NISAのつみたて投資枠へ、旧一般NISAは新NISAの成長投資枠へ、それぞれ2023年12月時点での積立設定が2024年の1月から引き継がれます。
これを知らずに、「新NISAが勝手に始まっていた」と戸惑っている人もいるようです。
なお、成長投資枠では、毎月分配型の投資信託など新たに対象外になった銘柄があります。
もし、成長投資枠で対象外の銘柄を一般NISAで積み立てていた場合は、引き継がれずに停止しています。
誤解②:旧NISA投資分は売却したほうがよい
旧NISAでの投資分は、急いで売却する必要はありません。そのまま持ち続けたほうがよい場合が多いです。
旧NISA(つみたてNISA、一般NISA)は2024年1月から、新規購入が停止しています。
ただし、2023年までに購入した銘柄は、保有し続けることができます。
旧NISAと新NISAの関係性がわかりにくいと感じる人も多いようですが、「新旧NISAは別々のハコである」と考えるとイメージしやすいと思います。
旧NISAのハコには、2024年以降は新たに商品を入れることはできませんが、すでにハコに入っている商品はそのまま置いておくことができるということです。
そして2024年からは、つみたて投資枠、成長投資枠という2つのハコが提供されていて、今後はこれらの新しいハコに商品を入れていきます。
旧NISAのハコに入っている商品(投資信託や株式)は、保管中にも値動きしています。
したがって、値上がりすれば当然増えていくのです。
ちゃんとした商品(分散されたインデックス投資信託など)であれば、そのままずっと持ち続けてもOKです!
また、旧NISAの非課税期間には、つみたてNISAが20年間、一般NISAが5年間という制限がありました。
「非課税期間を過ぎると利益に税金がかかってしまうから、非課税期間が終わるまでに売却しなければいけない」と考える人も多いです。
これは半分は合っていて、半分は間違っている認識です。
正確には、非課税期間内に増えた分には税金がかからず、非課税期間が終わってから増えた分のみに税金がかかります。
たとえば、つみたてNISAに年間上限の40万円投資していて、非課税期間が終わる20年後に100万円になっていた(60万円増えた)とします。
非課税期間が終わってから売却しても、増えた60万円は非課税で受け取ることができます。ただし、さらに増えて120万円になってから売却すると、100万円との差額である20万円分にだけ課税される、という仕組みです。
誤解③:2つの投資枠は併用不可
新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠は同時に利用可能です。
別々に開設手続きをする必要もありません。2つのハコが提供されるイメージです。
商品を購入するときに、どちらのハコに入れるかを選択すればよいのです。
2つのハコの使い分けに関しては、年齢や投資経験に関わらず、まずはつみたて投資枠からの利用をおすすめします。
これには2つ理由があって、1つ目は生涯投資上限額が増えるからです。
新NISAでは、生涯に投資できる金額に上限が設けられています。もし成長投資枠のみ利用の場合は、生涯投資上限額が1,200万円であるのに対し、つみたて投資枠を利用すれば生涯投資上限額が1,800万円となります。
2つ目の理由は、商品選択が比較的やりやすい点です。
つみたて投資枠では、手数料が安いなど金融庁が定めた条件を満たした投資信託のみが対象となっており、投資対象が多い成長投資枠と比べて選びやすくなっています。
投資金額で考えると、毎月の積立額が5万円未満の人は、つみたて投資枠のみの利用で良いと思います。
一方、毎月5万円以上の積立ができる人は、成長投資枠の利用も検討しましょう。
成長投資枠の利用方法については、以下の記事で詳細に解説しています。
誤解④:成長投資枠は積立投資ができない
つみたて投資枠では、積立購入のみ可能となっています。
一方、成長投資枠では一括購入と積立購入のどちらでも選択することができます。
50代以上の方から、「若い人ほど長期積立ができないので、成長投資枠で一括投資したい」というご相談をいただくことがあります。
このようなご相談に対しては、一括投資ではなく、積立投資をおすすめしています。
なぜなら、一括投資は値下がったときのダメージが大きいからです。
積立投資であれば、たとえ値下がっても「安く買える」ことになるので、安心して継続しやすいのです。
ただし、若い人ほど長期積立が出来ないことも事実ですので、まとまった資金がある場合は、2年~5年程度の期間で積み立てることを推奨しています。
「一括投資」と「長期積立」のちょうどあいだをとるような戦略ですね。
このとき、積立期間は2年~5年ですが、積立が終わった後はできるだけ長期保有することが前提です。
長く保有し続けたほうが、元本割れの可能性が減り、しっかり増えることは投資の原理原則です。
誤解⑤:NISAより良い投資商品がある
NISAは投資の利益に税金がかからないという仕組み(=ハコ)であり、投資商品ではありません。
ハコに入れるものは、色んな投資対象の中から選択できるのです。
したがって、「NISAのほかに、もっとよい投資商品はありますか?」という質問は、ちょっと不正確なのですね。
もちろん、どんな投資対象や商品でもNISAのハコに入るわけではありません。
NISAの対象外である投資対象も世の中にはたくさんあります。
それでも私は、資産運用するならNISAを利用したインデックス投資が、ほとんどの人にとっては最適解だと思っています。
インデックス投資の特徴を簡単にいうと、「すぐには増えないけれど、10年~20年という時間をかければ成功確率がかなり高くなる投資方法」となります。
「すぐに増やしたい、収入を得たい」と考えて、インデックス投資以外を選択する人もいます。
しかし、短期目線の投資は、労力をかけた割にうまく増やせなかったり、最悪の場合は大きく資産を減らしてしまったりする可能性もあることを、知っておいていただければと思います。
まとめ
新NISAでよくある5つの誤解についてご紹介しました。
旧NISA(つみたてNISA、一般NISA)から利用している人は、新NISAへの移行手続きや、移行後の旧NISA口座の取り扱いについて誤解されているケースが多いです。
旧NISAと同じ金融機関で、新NISAは自動的に開設され、一部の例外を除いて積立設定もそのまま引き継がれます。
また、旧NISAで投資した銘柄は引き続き非課税で保有できるため、すぐに売却する必要はありません。
新NISAでは投資枠が2つあるのも、わかりにくい要因となっています。
つみたて投資枠と成長投資枠はどちらも利用することができ、投資歴や年齢にかかわらずまずはつみたて投資枠から利用するのがお勧めです。
投資額がある程度大きくなる人は、成長投資枠も併用するとよいでしょう。
最後に、NISAは投資手段ではなく投資商品を入れる「ハコ」であるため、どんな商品をハコに入れてどのように管理するかが重要となります。
NISAの対象ではない投資手段もいろいろあります。
しかし、投資の利益にかかる税金が免除されるというNISAメリットはとても大きく、ほとんどの人にとっては資産運用をやるならNISAの投資対象から選択するのが最適解だと私は思っています。
投稿者プロフィール

- 老後の安心を育てる🌱資産形成・お金のパートナー
- 「人に教える仕事がしたい」という想いから会社を辞めて独立し、以前から取り組んでいた投資の知識を活かして資産運用講座をスタート。ところが、受講者の多くが抱えている老後資金への不安を解消するには、資産運用の知識だけでは不十分であり、家計や保険、年金など幅広い「お金の知識」が必要なことに気づく。そこで、お金の専門家であるFP資格を取得し、一人ひとりの状況に応じたサポートを開始。FPとしての専門知識を深めることで「寄り添ってもらえる」「安心して相談できる」と評価されるようになり、成長を遂げる。現在は、主に老後資金への不安を抱える女性に対して、完全に独立したFPとして中立な立場でのFPコンサルタントを通して、適切な家計管理や資産形成をサポート、自由で豊かな老後を実現していただくための基盤づくりに貢献している。また、学びのマーケット「ストアカ」の講師として650名以上に対し資産運用などを教える講座を開催し、最高ランクのバッジである「プラチナ」を取得。現在も引き続き講師活動を展開している。
最新の投稿
 資産運用2024年6月17日「元本割れなし」の個人向け国債が金利0.69%に上昇!
資産運用2024年6月17日「元本割れなし」の個人向け国債が金利0.69%に上昇!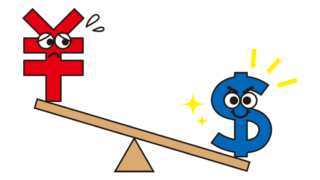 資産運用2024年6月10日今さら聞けない!円安と円高はどう違う?
資産運用2024年6月10日今さら聞けない!円安と円高はどう違う? フリーランスの日常2024年6月1日「ドーミーイン芸人」に触発されて
フリーランスの日常2024年6月1日「ドーミーイン芸人」に触発されて NISA2024年5月21日知らないと損する!投資信託に関する5つの誤解を解説
NISA2024年5月21日知らないと損する!投資信託に関する5つの誤解を解説
お問い合わせ
お悩み・お困りごとは、
お気軽にお問い合わせください