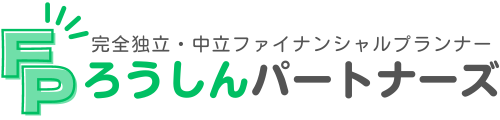投資信託協会のまとめによると、2024年3月末時点での公募投資信託の純資産総額は227兆円となり、過去最高を更新しています。
日本の成人人口をざっくり1億人として割り算すると、一人あたりの投資信託保有残高は227万円となります。
このような数字をみると、投資信託がずいぶん浸透してきているなと感じます。
投資信託残高の上昇には、2024年からリニューアルされたNISA制度を利用する人が増えていることも寄与しているようです。
その一方で、投資信託という「金融商品」についてあまり理解しないままに、NISAで投資信託を保有している人が多いように思います。
実際、私のところにも投資信託に関するさまざまな疑問が寄せられます。そこで、今回は投資信託についてよくある誤解を5つご紹介します。
- 1. 誤解① プロが運用してくれるから安心
- 1.1. 投資信託は分散投資を代行してくれるしくみ
- 1.2. 投資判断をするのは投資家本人
- 2. 誤解② 積み立てを止めると増えない
- 2.1. 「投資信託の積み立て」とはなにか?
- 2.2. 投資信託は保有しているだけで増える
- 3. 誤解③ 価格が高いほうが良い
- 4. 誤解④ 最悪の場合は価値がゼロになる
- 4.1. インデックス投資信託は分散投資の極み
- 4.2. 投資信託の資産は「分別管理」される
- 4.3. 投資者保護基金による1,000万円の補償あり
- 5. 誤解⑤ 円安対策は外貨預金(保険)のほうがよい
- 5.1. 超円安のとき外貨預金(保険)に加入するのは超危険!
- 5.2. 円安対策こそ投資信託が正解
- 6. さいごに
誤解① プロが運用してくれるから安心
一つ目の誤解は、「投資信託はプロが運用してくれるから安心」という言葉です。
このフレーズは、投資信託を販売したい金融機関等の営業トークとして使われることが多いです。
投資信託は分散投資を代行してくれる便利なしくみですが、安心して資産を増やせるかどうかは自分次第です。
投資信託は分散投資を代行してくれるしくみ
投資信託は、運用会社がたくさんの投資家からお金を集めて、株式や債券などに分散投資するしくみになっています。
投資家にとっては、1つの銘柄に投資するだけで、多くの対象に分散投資できることがメリットです。
また、保有しているだけで、投資対象の入れ替えも自動的に行ってくれます。
投資判断をするのは投資家本人
一方で、たくさんある投資信託のなかから、よいものを見極めるのは投資家自身が行います。
最初の銘柄選びで間違えてしまうと、せっかく長く保有しても結果が伴わないことになってしまいます。
また、投資信託を「いつ買うか」、「いくら買うか」、「いつまで保有するか」、「いつ売るか」など、投資判断をするのも自分です。
銘柄選びや投資判断についての知識を持ってはじめて、安心して投資信託を運用できるということですね。
誤解② 積み立てを止めると増えない
二つ目は、「積み立てを止めると増えない」という誤解です。
これは、「投資信託を積み立てる」という行為と、「投資信託を保有する」という行為の違いが理解できていないために生じる誤解です。
「投資信託の積み立て」とはなにか?
「投資信託の積み立て」とは、毎月決まった金額を自動的に購入し続けるしくみを利用することです。
たとえば、毎月3万円を積み立てるとしましょう。
一ヶ月目は3万円分の投資信託を新規購入します。購入した投資信託は、毎営業日ごとに価格が変化していきます。
二ヶ月目は、3万円分の投資信託を新規購入し、一ヶ月目に購入した分の保有残高(時価なので3万円より少し多いか少ないかの金額)に上乗せします。
三ヶ月目は、3万円分の投資信託を新規購入し、一ヶ月目と二ヶ月目に購入した分の保有残高(6万円より少し多いか少ないかの金額)に上乗せします。
積立設定を変更しないかぎり、翌月以降も同じことが繰り返されます。
投資信託は保有しているだけで増える
積立投資を数年続けて、積立設定を停止したとしましょう。
それ以降は、3万円の新規購入は実施されませんが、過去に購入した分は(自分が売らない限り)保有残高として残り続けます。
投資信託の価格は毎営業日ごとに変化していますので、長期的に値上がりしていけば、自分の保有残高も増えていくわけです。
誤解③ 価格が高いほうが良い
三つ目は「投資信託を選ぶとき、価格が高いほうが良い」という誤解です。
実際には、投資信託を購入するときの価格自体は、銘柄の良し悪しを決める判断材料にはなりません。
大事なのは「売却するときに、自分が買ったときよりどれだけ値上がりしているか」ということだからです。
ついでに言うと、「保有中の値動き」にも意味はありません。
たとえば1万円のときに購入した投資信託が、保有中に7,000円まで値下がることもあるかもしれませんが、売却しない限りは損をしません。
値上がって3万円になったときに売却すれば、その時点で3万円-1万円=2万円の利益が確定します。
誤解④ 最悪の場合は価値がゼロになる
四つめは、「最悪の場合は投資したお金がすべてなくなることもある」という誤解です。
さまざまな理由で、投資信託(とくにインデックス型の投資信託)の価値がゼロになる可能性は極めて低いと言えます。
インデックス投資信託は分散投資の極み
インデックス型投資信託の場合、投資先は数百~数千もの会社の株式に分散されていたり、世界中の国々の債券(国債)に分散されていたりします。
経済不況などさまざまな理由によって大きく値動きをすることはあっても、多くの投資対象に分散されているため、すべてが無価値になる可能性は限りなく低いといえます。
投資信託の資産は「分別管理」される
投資信託を購入したときの資産は、信託銀行と呼ばれる金融機関で「分別管理」されます。
したがって、もし信託銀行が倒産しても、原則として投資家の資産は償還(返却)されます。
分別管理とは、「投資家の資産を金融機関の資産とわけて管理する」という法律による義務づけです。
投資者保護基金による1,000万円の補償あり
さらに、証券会社は「投資者保護基金」という保険への加入義務があります。
もし分別管理が適切になされておらず、返却困難な状況に陥ったとしても、投資者保護基金により一人あたり1,000万円までの金銭が補償されます。
なお、SBI証券や楽天証券などのネット証券は投資者保護基金に加入しているのに対し、銀行は加入していません。
誤解⑤ 円安対策は外貨預金(保険)のほうがよい
五つ目は「円安対策として外貨預金や外貨建て保険がよい」という誤解です。
これは完全に、保険外交員や金融機関のセールストークなので注意しましょう。
超円安のとき外貨預金(保険)に加入するのは超危険!
2024年5月現在、為替相場は1ドル155円と歴史的な円安になっています。
円安(ドル高)になっている原因のひとつとして、日本とアメリカの金利差が大きくなっていることがあります。
また、米国金利が高いため、「利率がよい外貨預金や外貨建て保険に加入しませんか?」という勧誘が増えています。
しかし、歴史的な円安ということは、近い将来に円高へのぶり返しが発生する可能性があります。
もし円高になったら外貨建て資産は大きく値下がりすることになり、利息分の利益などあっという間に吹き飛んでしまいます。
円安対策こそ投資信託が正解
もし、外貨預金(保険)に加入したあとに円高になり、大きく価値が下がったらどうすればよいと思いますか?
正解は、「再び円安になるまで待つ」です。
為替は上がったり下がったりしますので、ずっと待っていれば、いつかはふたたび円安になる可能性が高いと思います。
しかし、それがいつになるかは誰にもわかりません。来年かもしれないし、10年後かもしれません。
かなり長く保有することを覚悟しておかなければなりません。
そして、同じ長期保有なら、外貨預金(保険)より海外の株式などを対象とした投資信託のほうが有利です。
なぜなら、株式は長く保有するほど大きく増えやすいため、(長期的には)為替による値動きの影響を受けにくい性質があるからです。
それに、海外資産を対象とした投資信託は、円安になれば価格が上がって「為替差益」が得られるので、円安の恩恵をちゃんと享受できます。
将来への円安対策こそ、外国株式や外国債券などを対象にした投資信託を、NISAやiDeCoを利用して保有することをお勧めします。
さいごに
投資信託でよくある5つの誤解を紹介しました。
「ぜんぶ知ってたよ!」という人がいたら、投資信託マスターの称号を(私が勝手に)お渡しします。
逆に、知らないことが多かったら、お伝えした内容をより一層の安心につなげていただければ幸いです。
正しい知識を増やし、『将来の価値を生む資産』として投資信託を長く持ち続けていきましょう。
投稿者プロフィール

- 老後の安心を育てる🌱資産形成・お金のパートナー
- 「人に教える仕事がしたい」という想いから会社を辞めて独立し、以前から取り組んでいた投資の知識を活かして資産運用講座をスタート。ところが、受講者の多くが抱えている老後資金への不安を解消するには、資産運用の知識だけでは不十分であり、家計や保険、年金など幅広い「お金の知識」が必要なことに気づく。そこで、お金の専門家であるFP資格を取得し、一人ひとりの状況に応じたサポートを開始。FPとしての専門知識を深めることで「寄り添ってもらえる」「安心して相談できる」と評価されるようになり、成長を遂げる。現在は、主に老後資金への不安を抱える女性に対して、完全に独立したFPとして中立な立場でのFPコンサルタントを通して、適切な家計管理や資産形成をサポート、自由で豊かな老後を実現していただくための基盤づくりに貢献している。また、学びのマーケット「ストアカ」の講師として650名以上に対し資産運用などを教える講座を開催し、最高ランクのバッジである「プラチナ」を取得。現在も引き続き講師活動を展開している。
最新の投稿
 資産運用2024年6月17日「元本割れなし」の個人向け国債が金利0.69%に上昇!
資産運用2024年6月17日「元本割れなし」の個人向け国債が金利0.69%に上昇!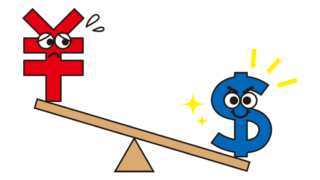 資産運用2024年6月10日今さら聞けない!円安と円高はどう違う?
資産運用2024年6月10日今さら聞けない!円安と円高はどう違う? フリーランスの日常2024年6月1日「ドーミーイン芸人」に触発されて
フリーランスの日常2024年6月1日「ドーミーイン芸人」に触発されて NISA2024年5月21日知らないと損する!投資信託に関する5つの誤解を解説
NISA2024年5月21日知らないと損する!投資信託に関する5つの誤解を解説
お問い合わせ
お悩み・お困りごとは、
お気軽にお問い合わせください