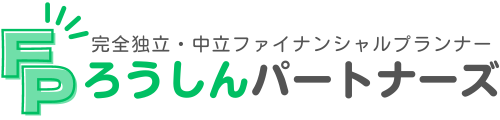2024年3月19日の金融政策決定会合で、日銀はマイナス金利政策の解除を決定しました。
マイナス金利政策とは、世の中にお金が回りやすくなるように、当座預金の一部にマイナス0.1%の金利をつけるというものです。
この決定を受けて、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行などの大手銀行が、預金金利の引き上げを開始しています。
2024年3月から4月にかけて、これまで0.001%だった普通預金金利が0.02%と20倍になります。
ただし、20倍になったとはいえ、金利0.02%というのはわずかなものです、、、
たとえば100万円の預金に対して、年間で得られる利息はわずか200円(税引前)です。
これでは物価の上昇(インフレ)に対して、まったく歯が立ちません。
ニッセイ基礎研究所の「2023~2025年度経済見通し」によると、国内の物価上昇率は以下のように予想されています。
消費者物価=コアCPI(生鮮食品を除く総合)
2023年:2.8%
2024年:2.0%
2025年:1.4%
物価上昇のペースは鈍化していくと予想されているものの、それでも銀行金利よりはるかに高い水準です。
このような時代に、銀行預金だけに偏った資産形成はリスクが高いといえるでしょう。
銀行預金も元本割れする?
「元本割れする(損をする)のが怖いから投資はしない」、という人は多くいます。
しかし、預金金利0.02%、物価上昇率1.5%がずっと続いたらどうなるでしょうか?
預金金利0.02%の場合、100万円の預金に対して10年間で得られる利息の合計は2,000円であり、元利合計は100万2,000円(税引前)となります。
一方、物価上昇率1.5%の場合、100万円のモノやサービスの値段は10年後に116万円に上昇します。
言いかたを変えると、現在の銀行預金100万円の価値は、10年後には約86万円に下がってしまうことになるのです。
数字上は同じ100万円であっても、インフレが続けば銀行預金は実質的に元本割れするのですね。
物価上昇(インフレ)に対応するために
物価上昇(インフレ)への対策は、NISAを用いた資産運用が最適だと思います。
NISAのメリットを2つに要約すると、次のようになります。
①長く続けるほど増えやすくなる
②生涯にわたり税金がかからない
投資対象を間違わなければ、NISAは長く続けるほどしっかり増やせる手段となります。
時間が経つほどに、物価上昇を大きく上回る可能性があがっていきます。
また、税金がかからなというのは、手取り利益が増えるというだけでなく、確定申告などの納税手続きが必要ないという意味においても、他の資産運用と比べてかなり有利であるといえます。
一方で、NISAにも弱点はあります。
①ある程度の知識が必要
②時間をかける必要がある
ある程度の知識とは、投資の3原則(分散・積立・長期)を理解したうえで、自分にあった投資計画や資産配分を決めていくための知識です。
また、投資というのは短期間で成果を出そうとすると失敗する確率が高くなります。
10年~20年という時間スケールで取り組んでこそ、より確実に増やすことができるのです。
これらを踏まえておくことではじめて、NISAをうまく使うことができます。
資産形成も中庸であれ!
「中庸」とは「偏りがなく中立的であること」を意味する言葉です。
家庭の資産形成においても、中庸であることはとても大切だと私は思います。
銀行預金だけだと、物価上昇(インフレ)に負けて資産価値が目減りしてしまう可能性が高くなります。
一方で、NISAの威力を過信するあまり無理をして投資金額を増やすと、長続きせずに挫折してしまうかもしれません。
銀行預金だけ、NISAだけ、というように偏ることなく、両者のほどよいバランスを保っていくことが肝要です。
ひとつの考えや手段に偏ることなく中庸であることこそ、資産形成の成功の秘訣であり、これからの時代を生き抜く術だと思います。
投稿者プロフィール

- 老後の安心を育てる🌱資産形成・お金のパートナー
- 「人に教える仕事がしたい」という想いから会社を辞めて独立し、以前から取り組んでいた投資の知識を活かして資産運用講座をスタート。ところが、受講者の多くが抱えている老後資金への不安を解消するには、資産運用の知識だけでは不十分であり、家計や保険、年金など幅広い「お金の知識」が必要なことに気づく。そこで、お金の専門家であるFP資格を取得し、一人ひとりの状況に応じたサポートを開始。FPとしての専門知識を深めることで「寄り添ってもらえる」「安心して相談できる」と評価されるようになり、成長を遂げる。現在は、主に老後資金への不安を抱える女性に対して、完全に独立したFPとして中立な立場でのFPコンサルタントを通して、適切な家計管理や資産形成をサポート、自由で豊かな老後を実現していただくための基盤づくりに貢献している。また、学びのマーケット「ストアカ」の講師として650名以上に対し資産運用などを教える講座を開催し、最高ランクのバッジである「プラチナ」を取得。現在も引き続き講師活動を展開している。
最新の投稿
 資産運用2024年6月17日「元本割れなし」の個人向け国債が金利0.69%に上昇!
資産運用2024年6月17日「元本割れなし」の個人向け国債が金利0.69%に上昇!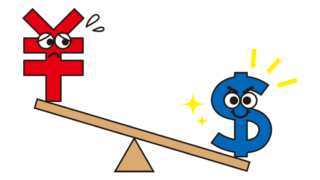 資産運用2024年6月10日今さら聞けない!円安と円高はどう違う?
資産運用2024年6月10日今さら聞けない!円安と円高はどう違う? フリーランスの日常2024年6月1日「ドーミーイン芸人」に触発されて
フリーランスの日常2024年6月1日「ドーミーイン芸人」に触発されて NISA2024年5月21日知らないと損する!投資信託に関する5つの誤解を解説
NISA2024年5月21日知らないと損する!投資信託に関する5つの誤解を解説
お問い合わせ
お悩み・お困りごとは、
お気軽にお問い合わせください