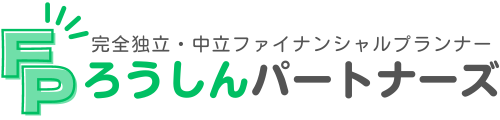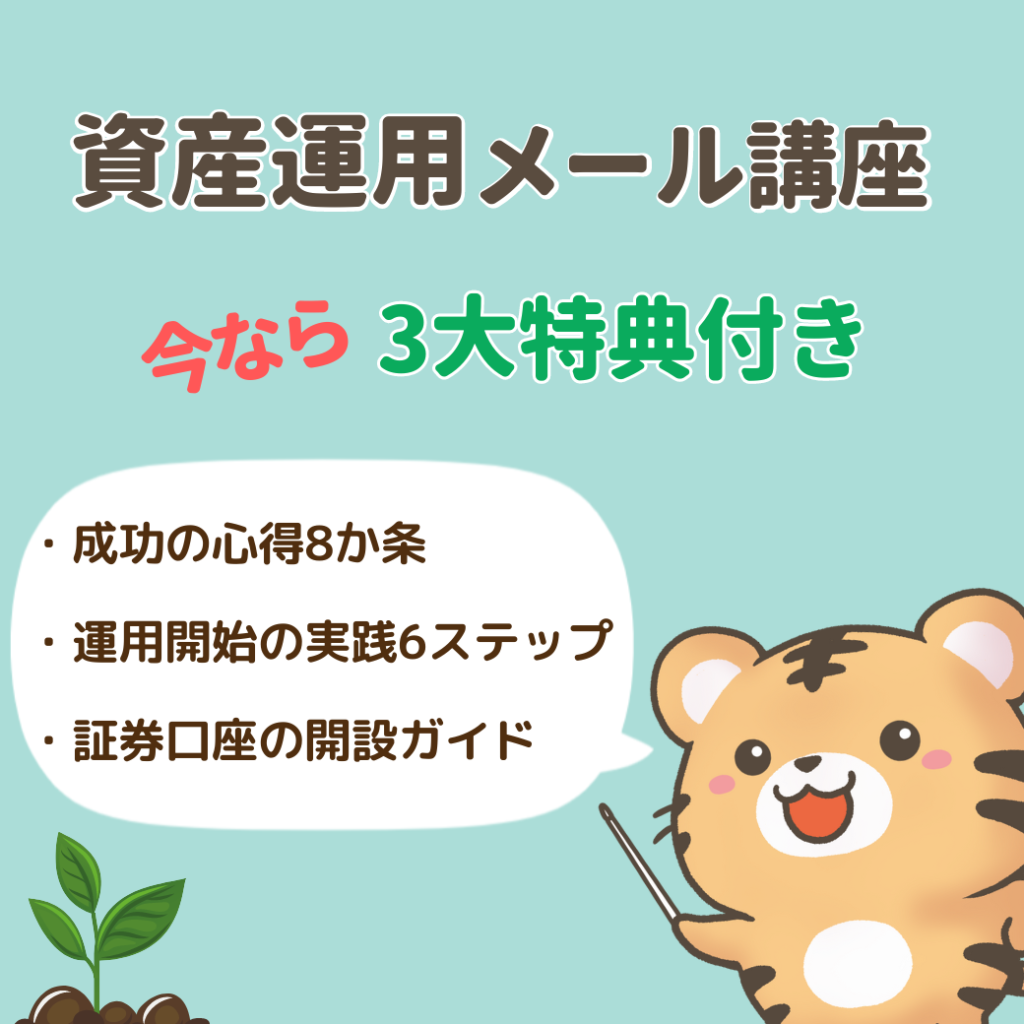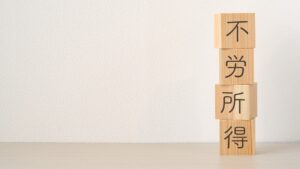2024年の1月から、NISA制度は新しく生まれ変わります。
非課税期間の恒久化や投資上限の増額など、個人の資産形成を大きく後押しする制度改革となります。
しかし、NISAはあくまで投資家を優遇する制度であるため、最低限の投資知識は持ったうえで始めないと思わぬ落とし穴にハマってしまうかもしれません。
そこで、新NISAスタートまであと少しとなったいま、2023年中に準備しておきたいことをシリーズでお伝えしていきます。
今回は、旧NISAから新NISAへの主な変更点、新NISA活用のポイントについて解説します。

2024年から新NISAが始まるって聞くけど、具体的になにがどう変わるのかしら?

投資できる金額が増える、ずっと非課税で運用できるなど、メリットが大きい変更だよ。この記事を読んで、ポイントをおさえておこう!
新NISAの変更ポイント概要
旧NISA制度は2023年12月末で終了となり、2024年の1月から新しい制度が開始されます。
新旧制度の概要を下表にまとめました。

また、新NISAの主な変更ポイントは以下のとおりです。
新NISAの主な変更ポイント
・投資可能期間、非課税期間が無制限になる
・つみたて投資枠と成長投資枠が併用できる
・年間投資上限額が合計360万円に増額される
・生涯投資上限額が1,800万円に増額される
・ジュニアNISAは廃止される
とくに重要な変更のポイントは、「制度の恒久化」と「投資上限の増額」です。
このどちらが欠けても、NISAの制度改革は中途半端なものになっていたでしょう。
ある程度まとまった資金を生涯にわたって非課税運用できるようになることで、今後は資産形成の重要な柱としてNISAを利用できるようになります。
以下、変更ポイントの詳細を順に説明していきます。
「生涯NISA」誕生のインパクトは大きい
2023年までの旧制度では、新規投資できる期間には制限があり、非課税期間も「一般NISA」が5年、「つみたてNISA」が20年という時限措置がありました。
新NISAでは、新規投資できる期間が恒久化され、投資上限額に到達するまでは何歳になっても新規投資できるようになります。
また、非課税期間も無制限になるため、将来いつ売却しても税金は一切かかりません。
「人生100年時代」と言われるように、長寿化とともにライフプランも多様化し、人生の資金計画も人それぞれに適したものを考える必要性が高くなっています。
そんな時代に、生涯非課税で投資できる新NISAの登場は、非常に歓迎できるものだと思います。
なお、確定申告など税金手続きを考えなくて良いことは、NISA制度恒久化の大きなメリットのひとつです。
一般的には老後資金として公的年金、個人年金、貯蓄型生命保険などがありますが、これらはいずれも課税対象となる可能性があります。
それに対して新NISAではごく一部の例外を除いて生涯非課税であり、税金周りの処理は基本的に必要ありません。
つみたてNISAと一般NISAの一本化
旧NISAでは、つみたてNISAと一般NISAのどちらか一方を選択するルールになっていました。
新NISAでは、つみたてNISAは「つみたて投資枠」、一般NISAは「成長投資枠」と名前を変え、両者が併用できるようになります。
投資できる商品と購入方法について
つみたて投資枠で投資できる商品は、つみたてNISAと同じく金融庁の基準をクリアーした投資信託が中心です。
金融庁の基準には、販売手数料がゼロ、信託報酬(運用管理手数料)が一定以下など、長期の資産形成に適した商品に限定されるような配慮がなされています。
商品選びの知識が少なくても、つみたてNISAやつみたて投資枠の対象商品から選ぶことで、いわゆる「ダメ商品」を避けることができます。
一方、成長投資枠で投資できる商品は、一般NISAと同様に株式や投資信託など幅広いラインナップとなります。
ただし、一般NISAとまったく同じではなく、「毎月分配型の投資信託」など一部の商品は成長投資枠の対象から除外されます。
成長投資枠の対象商品はまさに玉石混交であるため、商品選びにはより注意が必要です。
購入方法については、つみたて投資枠は「積立購入」のみが可能であるのに対し、成長投資枠では「積立購入」と「スポット購入(一括購入)」から選択することができます。
タイミングを見計らったスポット購入は難度が高いので、成長投資枠を利用するときも基本は計画的な「積立購入」を利用することをおすすめします。
年間投資上限額の違い
年間の投資上限額は、つみたてNISAの40万円/年から、つみたて投資枠では120万円/年と3倍になります。
月当たりでみると、つみたてNISAが3万3,333円/月と中途半端だったのが、つみたて投資枠では10万円/月とスッキリした金額になりました。
また、一般NISAの120万円/年から、成長投資枠では240万円/年と2倍になります。
既述のとおり、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠が併用できますので、両方を合わせた年間上限額は360万円/年です。
旧NISAと比べて、かなり大きな金額を新規投資できるようになりますね。
つみたて投資枠と成長投資枠、どちらを使う?
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠のどちらかのみを利用することもできるし、両方を同時に利用することもできます。
では、どのような基準でどちらを使うか判断すればよいでしょうか?
一つの明確な答えは、「投資初心者はつみたて投資枠から利用するべき」ということです。
選べる商品が長期投資に向いたものに限定されているつみたて投資枠を利用することは、初心者が堅実に資産を増やすためにとても重要となります。
ご年配の方であれば、「私は投資できる期間も短いし、つみたて投資枠ではなくて成長投資枠を利用するべきかな?」と思われるかもしれません。
しかし、年齢に関わらず、間違った商品選びをしないことを優先するべきです。
また、SBI証券や楽天証券のようなネット証券会社であれば、成長投資枠でもつみたて投資枠と同じ商品を選ぶことができます。
つまり、つみたて投資枠の年間上限である120万円より多く投資したい場合は、成長投資枠も利用してつみたて投資枠と同じ商品を積立投資すればよい、ということになるのです。
たとえば、年間投資上限まで利用する場合、次のような投資計画が考えられます。
【つみたて投資枠】
・投資信託Aを、毎月5万円積立購入する(60万円/年の投資)
・投資信託Bを、毎月5万円積立購入する(60万円/年の投資)
【成長投資枠】
・投資信託Aを、毎月10万円積立購入する(120万円/年の投資)
・投資信託Bを、毎月10万円積立購入する(120万円/年の投資)
これで、60万円+60万円+120万円+120万円=360万円の年間上限まで投資することが可能です。

「初心者はつみたて投資枠から利用する」は大事なキーワードね!

そうだね。つみたて投資枠だけで十分、という人も多いはず。自分に合った投資計画を立てることが大切だよ。
生涯投資上限は1,800万円になる
新NISAでは、生涯投資上限が1,800万円と定められました。
ただし、成長投資枠のみ利用する場合は1,200万円が生涯投資上限となります。
整理すると、各投資枠を利用する際の生涯投資上限額は以下のとおりです。
・つみたて投資枠のみ利用 ⇒ 1,800万円まで
・つみたて投資枠と成長投資枠の併用 ⇒ 1,800万円まで
・成長投資枠のみ利用 ⇒ 1,200万円まで
もし新NISAに生涯投資上限を設けなければ、お金持ちほど有利な制度となってしまいます。
そのため、一人あたりが投資できる金額には上限を設定するのですね。
生涯投資上限に到達するまでは、各個人が自分のペースで投資をすることができます。
積立額のケーススタディ
たとえば、つみたて投資枠を利用して毎月5万円を積立投資するとしましょう。
この場合、5万円×12ヶ月=60万円/年、60万円×30年=1,800万円となり、30年かけて生涯投資上限に到達します。
このケースのように、年間投資額が120万円以下であれば、つみたて投資枠のみを利用して生涯投資上限の1,800万円まで投資できます。
次に、つみたて投資枠と成長投資枠を併用して、毎月30万円と積立投資したらどうでしょう?
この場合、30万円×12ヶ月=360万円/年、360万円×5年=1,800万円となり、わずか5年で生涯投資上限に到達します。
すでにまとまった資金があるミドル以降の世代では、このような投資計画もあり得ます。
生涯投資上限額は簿価ベース
生涯投資上限額の1,800万円は、「簿価残高方式」で管理されます。
かんたんに言うと、投資できる元本が1,800万円までということ。
したがって、投資した後に資産が増えて1,800万円を超えたとしても、すべて非課税になります。
また、もし途中で資産の一部を売却したときは、その翌年に新規投資枠が復活します。
たとえば、ある年に100万円投資して、20年後に200万円に増えてからに売却したとします。
このとき、売却した翌年に復活する新規投資枠は200万円ではなく、元本分の100万円ということになります。
なお、この簿価残高方式はあくまで生涯投資上限に対して適用されるものであり、年間投資上限額には適用されないので注意しましょう。
年間投資上限(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)まで投資したあと、同じ年に売却して、NISAで再投資するということはできません。

とらひと先生!「簿価管理方式」の内容は理解するのがなかなか難しいわ💦

そうだよね。でも将来売却が必要になったときや、投資額が1,800万円を超えた後に関係することなので、最初は気にしなくて大丈夫と思うよ!
ジュニアNISAは廃止される
ジュニアNISAとは、未成年者のNISA口座をつくって、親などの親権者が代理で運用するしくみです。
新NISA制度には、ジュニアNISAは引き継がれないことになりました。
このため、2024年以降はジュニアNISA口座での新規投資はできません。ただし、2023年までに投資した分については、お子さんが成人するまで非課税運用を継続することが可能です。
ジュニアNISA廃止の理由については、私は次のように考えています。
廃止理由①:利用者数が伸びなかった
実際にジュニアNISAを利用している親御さんからは、「申し込み手順や仕組みが複雑でたいへんだった」という声を聞きます。
お子さん名義の未成年口座、ジュニアNISA口座を準備するなど、大人が自分でNISAを始めるよりも手続きが煩雑となるため、投資初心者にとってはハードルがより高くなります。
さらに、「非課税期間が5年で切れるためロールオーバー手続きが必要」、「成人するまで非課税で引き出しできない」など、不親切なルールが多いこともありました。
(ジュニアNISA廃止にともない、上記の不親切ルールは撤廃されたため、制度廃止前の「駆け込み申し込み」は増えているようです。)
このように使いにくい制度であったこともあり、利用者数が伸びず、制度を継続する意味合いが薄れたのではないかと推測します。
廃止理由②:新NISAの投資上限の増額
既述のとおり、新NISAでは投資上限額が大きく増えました。
成人一人につき生涯1,800万円ということは、夫婦二人で3,600万円の生涯投資上限を持てると考えることができます。
そのため、子供の教育資金についても、親の預金口座やNISA口座を利用して資産管理すればよい、ということができるでしょう。
まとめ
2023年12月末で旧NISAは終了し、2024年1月から新NISA制度がスタートします。
旧NISAでは投資可能期間や非課税期間に制限があったのに対し、新NISAでは制限が撤廃され「生涯NISA」が実現します。
また、年間投資上限は360万円、生涯投資上限は1,800万円と大きく増額され、子育て資金から老後資金まで幅広いニーズに対応できる、より実用的な制度に生まれ変わったといえます。
一方で、NISAはあくまで投資家を優遇する制度であるため、「投資を成功させるための最低限の知識」は必要です。
まずは制度のしくみを理解するとともに、投資商品や投資計画についても知識を持ったうえで、自分に合った資産運用をスタートさせていただければと思います。
投稿者プロフィール

- 老後の安心を育てる🌱資産形成・お金のパートナー
- 「人に教える仕事がしたい」という想いから会社を辞めて独立し、以前から取り組んでいた投資の知識を活かして資産運用講座をスタート。ところが、受講者の多くが抱えている老後資金への不安を解消するには、資産運用の知識だけでは不十分であり、家計や保険、年金など幅広い「お金の知識」が必要なことに気づく。そこで、お金の専門家であるFP資格を取得し、一人ひとりの状況に応じたサポートを開始。FPとしての専門知識を深めることで「寄り添ってもらえる」「安心して相談できる」と評価されるようになり、成長を遂げる。現在は、主に老後資金への不安を抱える女性に対して、完全に独立したFPとして中立な立場でのFPコンサルタントを通して、適切な家計管理や資産形成をサポート、自由で豊かな老後を実現していただくための基盤づくりに貢献している。また、学びのマーケット「ストアカ」の講師として650名以上に対し資産運用などを教える講座を開催し、最高ランクのバッジである「プラチナ」を取得。現在も引き続き講師活動を展開している。
最新の投稿
 資産運用2024年6月17日「元本割れなし」の個人向け国債が金利0.69%に上昇!
資産運用2024年6月17日「元本割れなし」の個人向け国債が金利0.69%に上昇!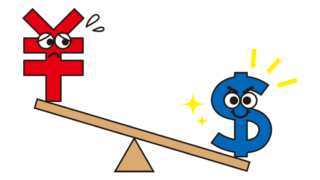 資産運用2024年6月10日今さら聞けない!円安と円高はどう違う?
資産運用2024年6月10日今さら聞けない!円安と円高はどう違う? フリーランスの日常2024年6月1日「ドーミーイン芸人」に触発されて
フリーランスの日常2024年6月1日「ドーミーイン芸人」に触発されて NISA2024年5月21日知らないと損する!投資信託に関する5つの誤解を解説
NISA2024年5月21日知らないと損する!投資信託に関する5つの誤解を解説
【購読無料】知って得する!「資産運用メール講座」のご案内
ろうしんパートナーズは、自由で豊かな老後を迎えたい女性のための「資産運用メール講座」を始めました!
- 資産運用、NISAに興味があるけれど、何から始めてよいかわからない
- 損をするのが怖くて投資に踏み出せない
- つみたてNISAを始めたけれど、このまま続けて良いのか不安
- お金のことを相談できる人がいない
こんなお悩むを抱えておられる方のための、より詳しく資産運用について学んでいただける、動画解説付きメール講座です。ご購読のお申し込みをされた方には、資産運用を始めるなら必ず知っておきたい「3大特典」をプレゼントしています。
メール講座の購読は無料です。下のボタンを押して、今すぐお申し込みください!