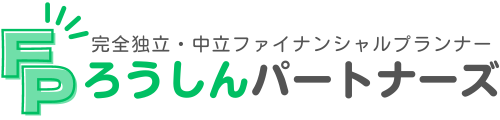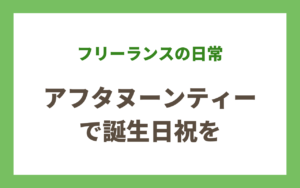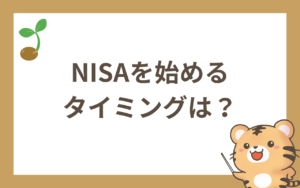最近、「プラチナNISA」や「子ども支援NISA」など、NISA制度の新たな提案がいくつかニュースに出てきています。
これらはまだ決定された制度ではなく、国会議員による提言の段階ではありますが、資産運用を始めたばかりの方にとっては気になる話題かもしれません。
今回は、その中のひとつ「子ども支援NISA」について、制度の内容を簡単にご紹介した上で、私自身の考えをお伝えしたいと思います。
子ども支援NISAってどんな制度?
子ども支援NISAについて、現時点で検討されている内容は次のとおりです。
- 現行NISA制度の「つみたて投資枠」の利用対象者を、未成年にも拡大する
つまり、「子どものための資産形成を、親ではなく子ども自身の名義で進められるようにする」という方向性です。
ちなみに、これまでも「ジュニアNISA」という制度がありましたが、こちらは2023年末で終了しています。今回の提言は、そのジュニアNISAの後継制度としての意味合いもあるようです。
子ども名義の口座、どう考える?
ここからは、制度の中身というよりも「子どものための資産をどのように管理するか?」という視点で、私の考えをお話しします。
たとえば、教育費のように金額が大きくなる資金について、「子どもの名義で運用する」必要が本当にあるのか? という点は一度立ち止まって考えてみてもよいと思います。
私自身は、基本的には「親の名義で管理するのがよい」と考えています。
理由はシンプルで、金額が大きくなりやすい教育資金は、子ども自身が責任を持って管理するには重たすぎるからです。
実際、「子どものためのお金だから分けて管理したい」という理由で未成年名義の口座を作る方も多いのですが、その場合でも親が管理するのであれば、親自身の名義で口座を分けるほうが合理的だと思います。
親のNISAで教育費を準備するという選択
現在のNISA制度では、親ひとりあたり1,800万円までの新規投資枠があります。夫婦であれば合計3,600万円まで投資が可能です。
この中で、「教育費も含めて親のNISAで一括して管理する」というのは、実はとても現実的な選択です。
「子ども用」と「老後用」などを分けて考えたい場合は、投資するファンドの種類を分けて管理することもできます。
もちろん、どんなファンドでも元本割れリスクを減らすには「長期保有」が必要ですので、子ども用ファンドも10年後以降に売却するような計画性は必要です。
資産をしっかり把握できていれば、名義にこだわらずとも、目的に沿った管理は可能なのです。
未成年口座は「金融教育」に使う
では、「未成年口座は一切使わないほうがよい」という話かというと、そうではありません。
私が考える未成年口座の役割は、「金融教育」です。
たとえば、銀行の未成年口座であれば、お小遣いを入金したり、お年玉を貯めたりしながら、預金や家計の基本を学ぶことができます。
また、ネット証券でNISA口座を利用すれば、100円から投資信託を購入することもできます。
実際に自分で投資商品を持つことで、「値動きとは何か」「投資にはどんなリスクがあるのか」など、教科書では学べない「経験」を身につけることができます。
「子どもが自分で管理できる金額で、自分で経験していく」。これが、未成年口座を活用する意味ではないかと私は思います。
子育て支援NISAはどう捉えるべき?
子育て支援NISAは、今のNISA制度では対応しきれていないニーズに応えようとする動きの一環かもしれません。
ただし、制度を複雑にすることで、かえって利用者が混乱してしまうリスクもあります。
大切なのは、制度を複雑にして選択肢を増やすことではなく、目的に合ったシンプルでわかりやすい仕組みを整えることではないでしょうか。
たとえば、掛け金の一部を所得控除できるような仕組みを、子育て世代に限定して導入するという方法は、より直接的な支援につながる可能性があります。
その意味でも、「子どものための資産管理をどうするか」については、親子それぞれに合った方法を選びながら、制度には必要に応じて柔軟に頼る、というスタンスが良いように思います。
最後に
教育費はもちろん大切ですが、「子どものお金の感覚を育てること」もまた、将来に向けての大切な土台になります。
制度の情報に振り回されることなく、「わが家にとってちょうどよい方法は何か」を考えるきっかけになればうれしいです。
投稿者プロフィール

- 老後の安心を育てる🌱資産形成・お金のパートナー
- 「人に教える仕事がしたい」という想いから会社を辞めて独立し、以前から取り組んでいた投資の知識を活かして資産運用講座をスタート。ところが、受講者の多くが抱えている老後資金への不安を解消するには、資産運用の知識だけでは不十分であり、家計や保険、年金など幅広い「お金の知識」が必要なことに気づく。そこで、お金の専門家であるFP資格を取得し、一人ひとりの状況に応じたサポートを開始。FPとしての専門知識を深めることで「寄り添ってもらえる」「安心して相談できる」と評価されるようになり、成長を遂げる。現在は、主に老後資金への不安を抱える女性に対して、完全に独立したFPとして中立な立場でのFPコンサルタントを通して、適切な家計管理や資産形成をサポート、自由で豊かな老後を実現していただくための基盤づくりに貢献している。また、学びのマーケット「ストアカ」の講師として650名以上に対し資産運用などを教える講座を開催し、最高ランクのバッジである「プラチナ」を取得。現在も引き続き講師活動を展開している。
最新の投稿
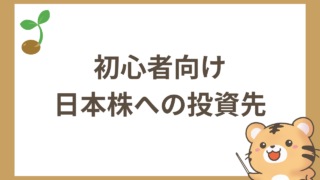 資産運用2025年11月27日日本株に投資するなら何を選ぶ?初心者がまず知っておきたいポイント
資産運用2025年11月27日日本株に投資するなら何を選ぶ?初心者がまず知っておきたいポイント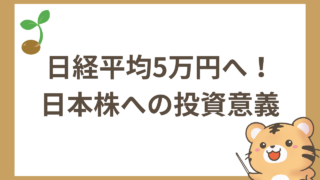 ろうしんパートナーズについて2025年11月20日日経平均5万円の時代、日本株を持つことの意義をあらためて考える
ろうしんパートナーズについて2025年11月20日日経平均5万円の時代、日本株を持つことの意義をあらためて考える 資産運用2025年11月6日なぜ外貨建て保険に入るべきではないのか――金融機関が言わない本当のリスク
資産運用2025年11月6日なぜ外貨建て保険に入るべきではないのか――金融機関が言わない本当のリスク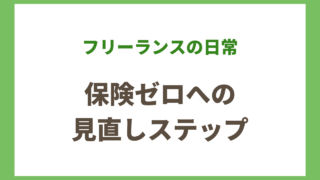 フリーランスの日常2025年10月23日保険ゼロでも不安なし?私がたどった見直しのステップ
フリーランスの日常2025年10月23日保険ゼロでも不安なし?私がたどった見直しのステップ
お問い合わせ
お悩み・お困りごとは、
お気軽にお問い合わせください